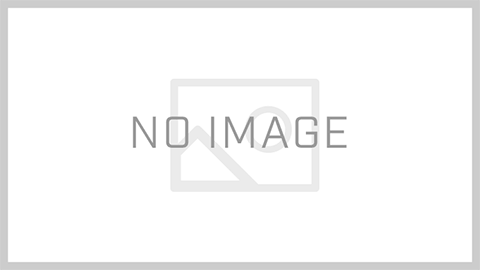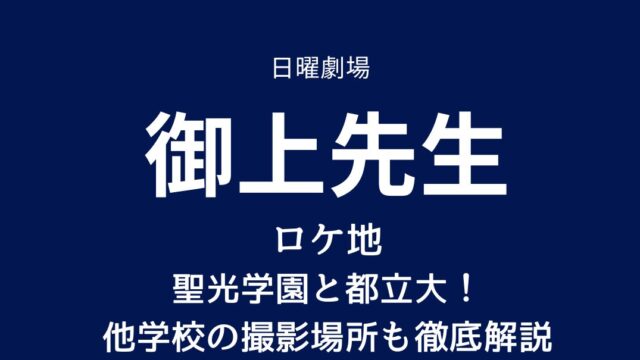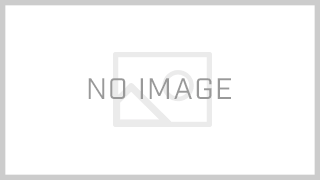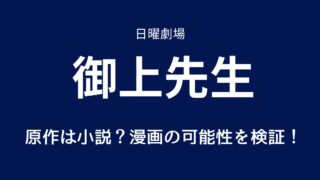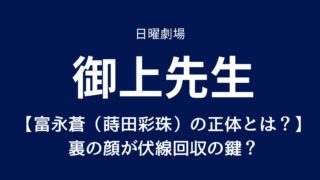ドラマ『御上先生』の最終回まで見届けた人の中には、きっとこんな疑問が残ったはずです。
なぜ御上先生は、わざわざ“問題の多い隣徳学園”に来たのか?
エリート街道を歩んでいたにもかかわらず、教育現場の“闇”とも言えるような場所に飛び込んでいった御上孝(松坂桃李)。
その真意は、ただの「改革精神」や「正義感」では語りきれないものがありました。
この記事では、御上先生が隣徳に来た“本当の理由”を、最終回の彼の言葉・行動・背景から読み解いていきます。
エリート街道のど真ん中にいた御上先生
まず大前提として、御上先生は超がつくほど優秀なキャリア官僚でした。
文部科学省でも重要なポジションにいて、教育政策の中枢にいた人物です。
本来なら、現場に降りる必要はなかった。
むしろ、現場を「動かす側」にいた彼が、なぜ自ら“火種だらけの教育現場”へ?
その選択には、個人的な想いと制度への疑問、そしてある“過去の後悔”が関係していたのです。
原点は「兄のような生徒を救いたい」という想い
最終回、神崎との会話で御上先生はこう語ります。
「一色先生から神崎の話を聞いて、兄に似ていると感じた」
御上の兄もまた、制度に潰され自死した“生徒”だったという過去。
御上が見てきたのは、現場で心が折れていく生徒たちの現実。
その中でも、兄のような“真面目で、傷つきやすい若者”が、大人の都合に巻き込まれて壊れていく姿だったのではないでしょうか。
隣徳学園という“制度の象徴”に乗り込んだのは、その構造の中にいる「過去の兄」とも重なる生徒を、今度こそ救うためだったのです。
「現場」を知らなければ、制度は変えられない
御上が官僚という立場を捨て、教壇に立ったのは、理想やスローガンだけでは変わらない“リアルな教育”を体感するため。
文科省から見えるのは、「データ」「数字」「実績」だけ。
でも、教室にはそれだけじゃない、生徒一人ひとりの葛藤がある。
「教室に立たなければ、本当に必要な教育改革はできない」
そんな強い覚悟が、御上先生を“現場”に立たせたのです。
「あえて隣徳を選んだ」=最大の挑発
隣徳学園は、いわば文部科学省と癒着した“教育の象徴”。
むしろ御上は、古代、中岡、塚田といった“自分がいた側”の人間に対して、「それでは生徒は救えない」と証明しに来た。
この構図は、まさに内部告発者のような姿でもあり、生徒たちを守るために、“味方のフリをした裏切り者”としての孤独な戦いだったとも言えるのです。
考えてみて――その言葉が向けられたのは、大人たちにも
御上先生が生徒たちに投げかけた「考えてみて」という言葉。
あれは、教室の中だけに向けたものではなかったと思います。
不正を見逃してきた教育者たち。
制度を黙認してきた行政。
そして、何も知らずに“当たり前”に乗っかっていた私たち大人自身に向けられた問いでもあったのです。
隣徳に来た理由――それは「生徒を導く」ためだけではなく、教育そのものにもう一度“問い直すため”でした。
まとめ:御上先生の選択こそが、教育改革の第一歩だった
御上先生が隣徳に来た理由は、単なる赴任でも左遷でもありません。
それは「現場を知らなければ、何も変わらない」という強い決意のもと、教育という構造そのものに、身体を張って向き合った一人の大人の覚悟でした。
あの教室で、彼が静かに、そして誠実に問い続けたすべての言葉は――
これからの教育を、私たち自身が“自分事”として考えるための、最初の一歩だったのかもしれません。
 関連記事
関連記事
隣徳学園に根付いた構造的腐敗と、大人たちの責任とは?御上先生が向き合った“教育の病巣”を解説。

「考えてみて」というメッセージの本質に迫る。御上先生が私たちに残した問いの意味とは?